表彰記念品 ― レリーフ原型づくりの大切な工程
表彰記念品として、レリーフ盾や記念レリーフ額などを企画・制作する際には、その核となる「レリーフ原型」の制作が極めて重要な工程となります。
どれほど高品質な素材や仕上げを用いたとしても、この原型が優れていなければ、最終的な作品の魅力は半減してしまいます。
今回は日本金属工芸研究所において、このレリーフ原型づくりについて、基本的な流れとその奥深さをご紹介いたします。
まずはデザインからスタート
レリーフ制作は、まず構想・意匠を練る段階から始まります。どのような人物や風景をモチーフにするのか、構図はどうするか、文字の配置や余白の取り方など、あらゆる要素をデザインとして落とし込みます。
これは単なる装飾ではなく、受け取る方に感動を届けるための大切な「表現」です。
この段階では、紙にスケッチを描く場合もありますし、近年ではデジタルデザインによる提案も増えています。
お客様のご希望やご用途に応じて、記念の意味が伝わるようなデザイン構成を心がけます。
原型制作 ― 「足す」か「削る」か
デザインが決まったら、いよいよ原型づくりに入ります。
レリーフの原型は、主に「粘土」または「木材」で制作されることが多いです。
粘土を用いる場合は、まっさらな台の上に粘土を盛っていきながら形を作ります。
柔らかく、加減しやすい素材のため、細やかな造形表現が可能です。粘土はまさに「足し算」の造形。
少しずつ盛っていくことで形を立ち上げ、表情や服のひだ、背景の細部まで丁寧に彫り込んでいきます。
一方で木を使う場合は、木の塊を削る「引き算」の手法となります。
彫刻刀やノミなどを駆使して、余分な部分を落としながら形を導き出していきます。
素材の硬さや木目の流れに逆らわず、素材の持ち味を活かすことが求められます。
実際には、粘土もある段階から不要な部分を削って整える作業が必要になりますし、木でも細かいパーツを貼り足すことがあります。
つまり「足し算」「引き算」の両方を巧みに使いこなすことが、原型師や彫刻家の腕の見せどころなのです。
原型から型を取り、石膏へと移行
粘土や木で完成した原型からは、「型取り」の作業に入ります。
これは、後に金属などで鋳造するための準備段階です。まず原型の表面にシリコンやゴムなどの型材を流し込み、ネガ(凹型)を作ります。
その型に石膏を流し込んで固め、ポジ(凸型)の石膏原型を得るのです。
この石膏原型は、さらに表面の微調整を加えられることもありますが、もとの原型がしっかりと表現されていなければ、最終的な製品に魅力が宿りません。
つまり、鋳造や仕上げの前段階であるこの「原型づくり」こそが、表彰記念品としての品質と価値を決める重要な鍵を握っているのです。
デザイン力と造形力が命
レリーフ原型を制作する際にもっとも問われるのは、「表現の力」です。写実的な人物像であれば、顔の特徴や衣服の流れ、髪の表現などをいかに自然に、かつ力強く表現できるかが重要です。
また、記念碑的なモチーフでは、荘厳さや品格、構図の安定感なども問われます。
そのためには、デザイン構成力、空間の取り方、造形技術、さらには長年の経験による"勘"のようなものも必要です。
特にレリーフは立体と平面の中間に位置するような芸術表現であり、そのバランス感覚が要求されます。
まとめ ― 原型こそが作品の魂
このように、レリーフ盾や記念レリーフ額といった表彰記念品を制作するうえで、原型づくりは単なる工程の一つではなく、作品の魂を形づくる最も大切な部分だと言えます。
完成された記念品が人々の目に触れるとき、その背後にはこうした丹念な原型制作の積み重ねがあるのです。
表彰記念品をお考えの際は、ぜひこの「原型づくり」の大切さにもご注目ください。
私たちは、ひとつひとつの作品に想いを込め、心を込めて制作にあたっております。
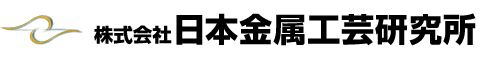
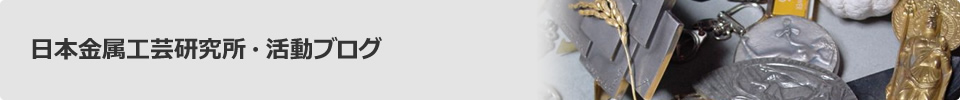
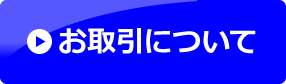


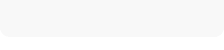
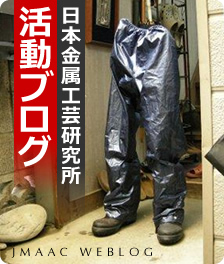
 付加価値が付いた記念品は、授賞に対する重さが感じられるはず。表彰、芸術に対する弊社の想いを掲載しています。
付加価値が付いた記念品は、授賞に対する重さが感じられるはず。表彰、芸術に対する弊社の想いを掲載しています。 企画・デザインから製造、装丁まで、お客さまのご希望のものが形になるまでの一連の流れについて説明しています。
企画・デザインから製造、装丁まで、お客さまのご希望のものが形になるまでの一連の流れについて説明しています。 オリジナル表彰盾やトロフィー、ブロンズ像、表彰記念品など、弊社自慢の納品実績を掲載しております。
オリジナル表彰盾やトロフィー、ブロンズ像、表彰記念品など、弊社自慢の納品実績を掲載しております。 弊社では、一点一点真心を込めてレリーフ額や表彰楯、胸像や肖像レリーフなどの彫刻作品を製作しております。
弊社では、一点一点真心を込めてレリーフ額や表彰楯、胸像や肖像レリーフなどの彫刻作品を製作しております。